「生成AI」がビジネスのあらゆる側面に浸透し始めています。
総務省の「令和6年版 情報通信白書」によれば、世界のAI市場規模は急速な拡大を続けており、日本国内でも生成AIの利用経験率は2割を超える(MM総研調査)など、その活用は一部の先進企業から一般的なビジネスシーンへと移行しつつあります。
このような背景から、「生成AIの作り方」への関心が高まっています。
しかし、このキーワードには「AIモデル自体を開発したい」という技術的な意図と、「AIに最適化されたWebコンテンツを作りたい(LLMO)」という戦略的な意図が混在しています。
当メディアの分析では、ビジネスにおける「生成AIの作り方」とは、これらどちらか一方を指すのではありません。
次の3つの異なるレイヤーを、自社の事業目的に沿って統合的に構築するプロセスそのものです。
- ①【技術】としてのAIモデル開発」
- ②【情報】としてのAI最適化コンテンツ(LLMO)
- ③【規範】としてのAIガバナンス(ルール)
この記事では、AI開発の具体的なアプローチから、戦略的な情報発信(Web最適化)、そして開発と利用に不可欠なリスク管理(ガバナンス)まで、実践的な第一歩を踏み出すためのロードマップをお伝えします。
- 「生成AIの作り方」に含まれる2つの主要な検索意図(モデル開発とLLMO)
- AIモデルを技術的に「作る」3つのアプローチ(API利用、ファインチューニング、自社開発)
- AIに最適化されたコンテンツ(LLMO)や安全な利用ルール(ガバナンス)を「作る」方法
1.「生成AIの作り方」で検索する2つの目的
「生成AIの作り方」というキーワードを検索する際、読者の皆様が求めている答えは、大きく分けて2つの側面に分類されます。
自社の目的がどちらに近いか、あるいは両方を求めているのかを認識することが第一歩です。

目的A:AIモデルそのものを「開発」したい
これは、最も直接的な「作り方」であり、技術的な側面を指します。
Pythonなどのプログラミング言語を使い、機械学習ライブラリ(TensorFlowやPyTorchなど)を用いて、独自のAIモデルを構築(スクラッチ開発)したり、既存のモデルを特定のタスクに適応(ファインチューニング)させたりする方法です。
このアプローチは、高度な専門知識と計算リソースを必要としますが、自社のビジネスに完全に特化した、独自の競争優位性を持つAIソリューションを実現できる可能性があります。
目的B:AIに最適化されたコンテンツを「構築」したい(LLMO)
こちらは、近年の検索エンジンの進化(SGE: 検索生成体験など)に伴い、急速に重要性を増している側面です。
AIモデルを「開発」するのではなく、AIが情報を理解し、引用・推薦しやすいように、自社のWebサイトやコンテンツを「構築(最適化)」する方法を指します。
これは、LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化) と呼ばれる新しい概念です。
AIが参照しやすいように情報を構造化し、その「作り方」を工夫することで、AIによる情報生成(検索結果など)において自社のコンテンツが優位に立つことを目指す、戦略的な取り組みです。
2.側面①:【技術】AIモデルを「作る」3つのアプローチ
「意図A」に該当する、AIモデルそのものを技術的に「作る」方法は、必要なリソースや専門性に応じて、主に3つのアプローチに分類されます。

アプローチ1:基盤モデルの「API利用」とRAG
最も現実的かつ迅速にAIを業務に導入する方法です。
OpenAIのGPTシリーズ、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeなど、他社が開発した高性能な基盤モデル(Foundational Model)をAPI経由で利用します。
このアプローチでは、AIモデル自体を「作る」のではなく、「AIを利用するアプリケーション」を作ります。
特に、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成) という技術と組み合わせることで、AIに自社独自の最新情報や専門知識(例:社内マニュアル、製品カタログ)を参照させ、事実に基づいた正確な回答を生成させることが可能になります。
アプローチ2:既存モデルの「ファインチューニング」
API利用の次に一般的なアプローチです。
「既存のオープンソースモデル(例:Llama 3)や、API提供されているモデル(一部)に対し、自社で用意した小規模な高品質データセットを追加学習させます」。
これにより、モデルの基本的な能力を活かしつつ、次のように特化させることができます。
- 特定の業界用語
- 特有の対話スタイル
- 専門的なタスク(例:法務文書のレビュー、特定のコーディング規約に沿ったコード生成)
API利用よりもコストと専門性が必要ですが、より自社のニーズに最適化されたAIを作ることが可能です。
アプローチ3:ゼロからの「自社開発」
「基盤モデルそのものをゼロから構築する」アプローチです。
膨大な量の学習データ、高性能な計算リソース(多数のGPU)、そしてAI研究者レベルの高度な専門知識が必要となります。
数年単位の時間と巨額の投資が必要となるため、大手テック企業や国家レベルのプロジェクト以外では現実的ではありません。
しかし、特定のドメイン(例:医療、金融、特定の言語)において、既存のモデルでは達成不可能な、全く新しい価値を生み出す可能性を秘めています。
3.側面②:【情報】AIに最適化されたコンテンツを「作る」(LLMO)
「意図B」に該当する、AI時代の新しいSEOとも言えるアプローチがLLMOです。
これは、技術的にAIを「開発」するのではなく、AIという「情報の利用者」に対して、戦略的に情報を「構築」する作業を指します。
LLMO(大規模言語モデル最適化)とは何か?
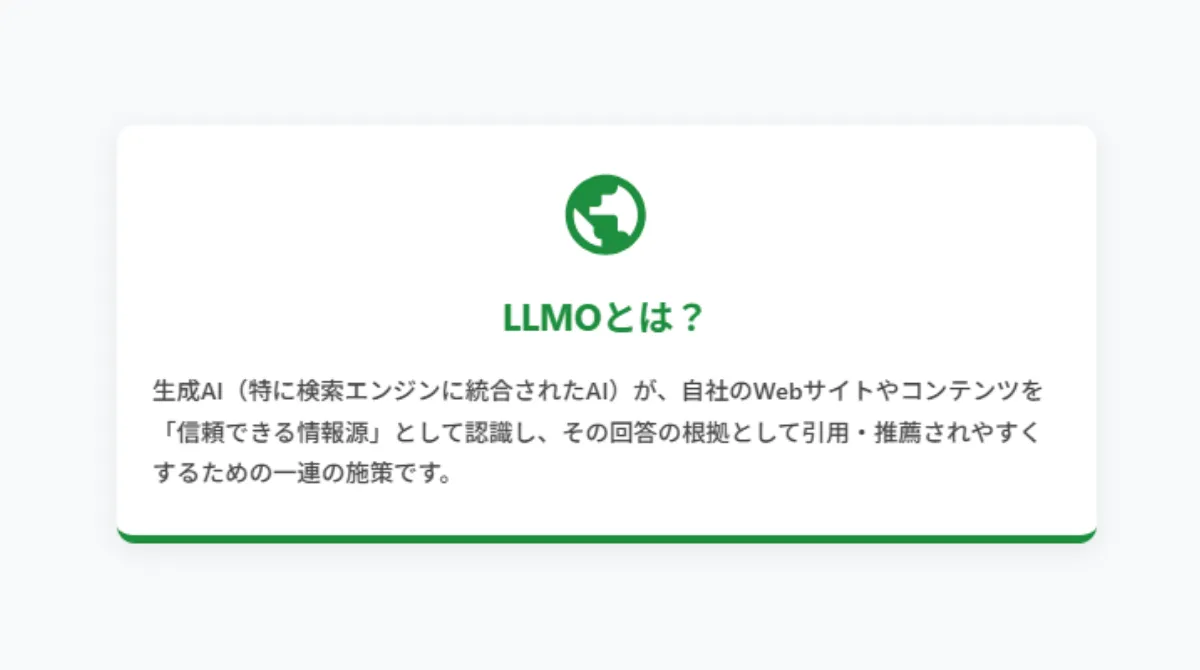
LLMOとは、生成AI(特に検索エンジンに統合されたAI)が、自社のWebサイトやコンテンツを「信頼できる情報源」として認識し、その回答の根拠として引用・推薦されやすくするための一連の施策です。
従来のSEOが「キーワード」と「検索順位」に焦点を当てていたのに対し、LLMOは「情報の正確性」「権威性」「文脈の明確さ」に焦点を当てます。
AIは、曖昧な情報や信頼性の低い情報源よりも、「明確で構造化された情報」を好むためです。
AIが理解しやすいWebサイトの構築(構造化マークアップの実践)
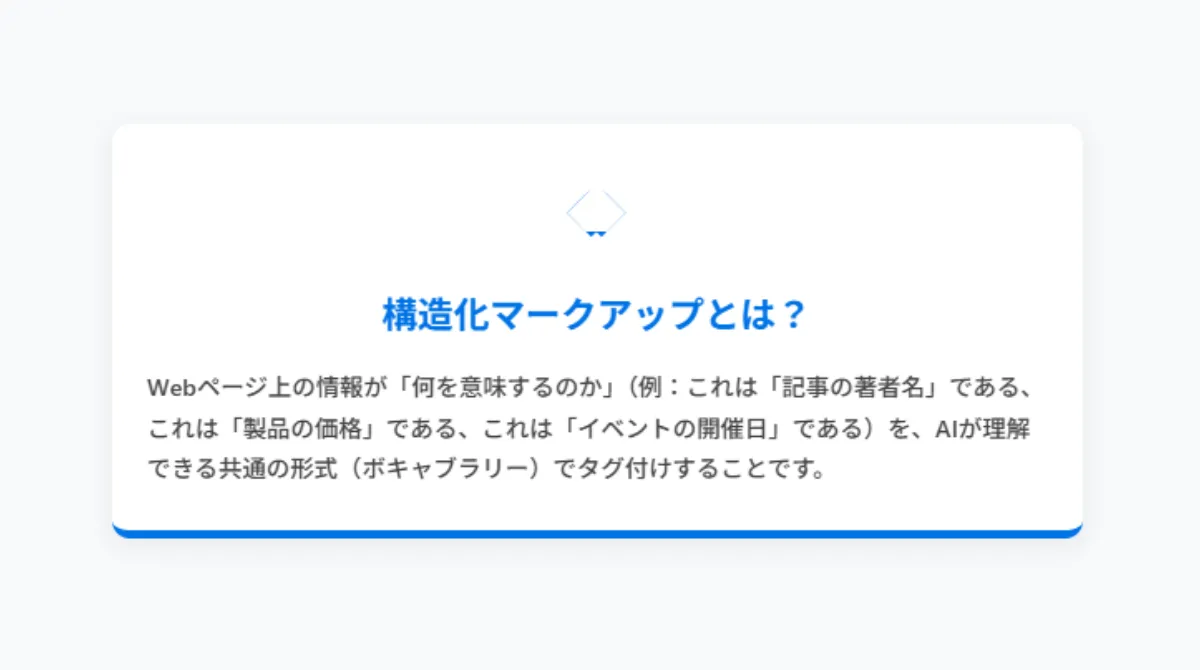
LLMOの具体的な実践方法として、SEO調査レポートでも上位記事が共通して言及していたのが「構造化マークアップ」の重要性です。
構造化マークアップとは、「Webページ上の情報が「何を意味するのか」(例:これは「記事の著者名」である、これは「製品の価格」である、これは「イベントの開催日」である)を、AIが理解できる共通の形式(ボキャブラリー)でタグ付けすること」です。
特にFAQ(よくある質問)の構造化マークアップ(FAQPageスキーマ)などは、AIがユーザーの疑問に対して的確な回答を生成する上で、非常に有効な情報源となります。
コンテンツを「作る」だけでなく、AIが理解できる形式に「構築」し直すことが、LLMOの核心です。
4.側面③:【規範】AIを安全に使うためのルール(ガバナンス)を「作る」

「技術」と「情報」のレイヤーを構築しても、それを利用するための「規範(ルール)」がなければ、AIは暴走するリスクを伴います。
ビジネスにおいて「生成AIを作る」とは、このガバナンス体制を「作る」ことを含みます。
なぜガバナンス構築が「作り方」の重要な一部なのか

生成AIは、ハルシネーション(嘘の情報を生成する)、学習データに含まれるバイアスの再生産、機密情報の漏洩、著作権侵害など、多くの法的・倫理的リスクを内包しています。
AIを「作る」開発者も、「使う」利用者も、これらのリスクを理解し、管理するための明確なガイドラインが必要です。
ガバナンスの構築は、技術的な失敗を防ぐだけでなく、企業の法的責任やレピュテーション(評判)リスクから守るための「安全装置」として機能します。
AI開発のリスク管理(ハルシネーション、セキュリティ、バイアス)
AIを安全に「作る」ためには、開発プロセスの初期段階からリスク管理を組み込む必要があります。
例えば、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)は「セキュアな AI システム開発のためのガイドライン」を公開しており、AI開発におけるセキュリティ(セキュアバイデフォルト)の重要性を説いています。
また、開発・利用の両面で参照すべき指針として、経済産業省などが公表している「AI事業者ガイドライン」があります。
これは、AIの安全性、公平性、透明性などを確保するために、AI開発者や提供者、利用者がそれぞれ取り組むべき責務を示したものです。
これらのガイドラインに基づき、自社独自のAI利用ポリシー(例:機密情報の入力を禁止する、AIの生成物は必ず人間がファクトチェックするなど)を策定・周知することが、規範を「作る」具体的なアクションとなります。
5.自社に最適な「AIの作り方」は目的主導で見つける
本記事では、「生成AIの作り方」というキーワードを、「①技術(モデル開発)」「②情報(LLMO)」「③規範(ガバナンス)」という3つの異なるレイヤーから解き明かしました。
「生成AIの作り方」に唯一の正解はありません。重要なのは、『企業向けAI導入プレイブック』で示されるように、「AIを使って何を達成したいのか」という目的主導のアプローチです。
自社のビジネス課題を解決するために、高度な「技術」開発が必要なのか、まずはAPI利用と「情報」の最適化(LLMO)から始めるべきなのか。そして、どのような「規範」のもとでそれを安全に運用していくのか。
これらの3つのを側面を自社の目的に合わせて統合的に「作る」ことこそが、AI時代における真の「生成AIの作り方」と言えるでしょう。





